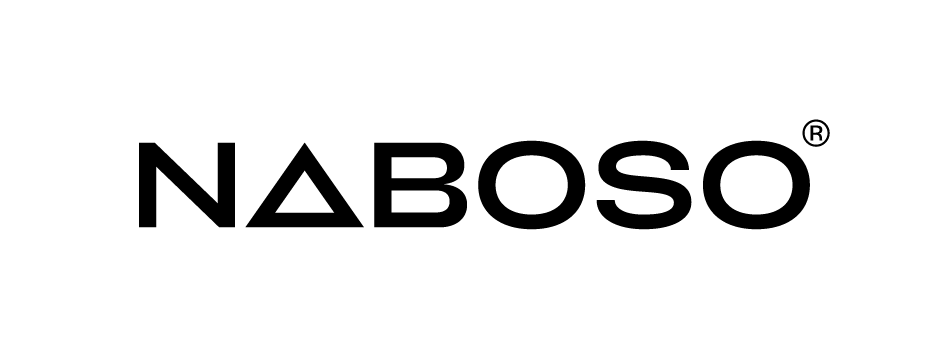「ボディスキーマ」とは
身体図式「ボディスキーマ」とは、私たちの脳が自分の身体の位置や動きを認識し、調整するための無意識のマップのようなものです。例えば、暗闇の中でも自分の手がどこにあるかを把握できたり、狭い場所を通る際に無意識に肩をすぼめたりするのは、この身体図式が機能しているからです。
ボディスキーマを説明するために私がよく使う例です。混雑したレストランで、トイレに行くために椅子とテーブルの間を歩いているところを想像してみてください。ふたつの椅子の間隔を見て、その間を通れるかどうかを判断できるのは、まさにボディスキーマの能力によるものなのです。
この身体図式は加齢や神経学的ダメージ(例:脳卒中など)によって低下することがあり、その結果、バランス感覚や協調運動が損なわれる可能性があります。しかし、適切な刺激を与えることで、身体図式の精度を向上させることが可能です。
触覚の適応力を高める
触覚の適応力を高めるトレーニングとは、脳が触覚刺激を受け取った際に、それをどの部位で感じたのかを正確に識別し、運動指令に反映させるプロセスを指します。例えば、立っている時に手にくすぐったさを感じてハエが止まっていることに気づき、それを払いのける際、手が身体の脇でリラックスしている場合と、食べ物が乗った皿を持っている場合とでは、反応が異なります。
手に軽い刺激を感じたとき、それがどの指に触れたのかを瞬時に把握し、適切な動作を行うことができます。この機能は、日常の動作だけでなく、リハビリや運動パフォーマンスの向上にも役立ちます。
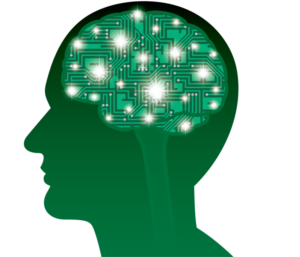
脳の可塑性と触覚刺激
脳は常に変化し、新しい情報を学習しながら適応する能力を持っています。これを「脳の可塑性」と呼びます。触覚刺激はこの可塑性を促進する重要な要素であり、特定の刺激を繰り返し与えることで、神経回路を強化し、身体図式の再構築をサポートします。
リハビリに触覚の適応力を高めるトレーニングを取り入れることで、身体図式と外部環境との関係における身体の協調性を高めることができます。この考え方は、神経可塑性に基づいています。
大脳皮質の機能は固定的ではなく、経験(刺激)によって絶えず変化することが明らかになっています。慢性期の脳卒中からの自然回復は、この可塑性によるものであり、損傷した大脳半球の再生が最良の回復をもたらすとされています。触覚による刺激は、脳の可塑性を高めるのに重要な役割を果たします。
触覚の適応力を高めるエクササイズ
リハビリや日常のケアに簡単に取り入れられるエクササイズをいくつかご紹介します。
エクササイズ① 手を組む
このエクササイズは、触覚の適応力を高めるトレーニングにおいて最も研究されているもののひとつです。
目を閉じて両腕を前に組み、手のひらを上下に動かします。片方の手のさまざまな部分に触れ、それが右手か左手かを識別します。強弱のある刺激や異なる触覚刺激(軽いタッチ、振動など)を取り入れることで、効果が向上します。
エクササイズ➁ 足裏への刺激
足裏刺激というと、つい地面に足がついた直立の状態の姿勢を考えてしまいますが、さまざまな姿勢で刺激を与えることも必要です。
四つん這いになって片足を持ち上げたり、座って片足首を膝の上で交差させたり、さまざまな姿勢をとります。足を見ていない状態で、その足裏に軽い刺激を与え、どの部分に触れたかを認識します。立った状態や歩行時にも同様の刺激を取り入れ、身体図式の強化を図ります。
エクササイズ③ 「ハンドアクティベーションキット」を使用した手のエクササイズ
ナボソの「ハンドアクティベーションキット」は、手と指の感覚を高めながらトレーニングすることで、筋肉を活性化させるために開発された製品です。独自のテクスチャーと人間工学に基づいたデザインにより、日常生活やトレーニングにおいて効果的に使用できます。
キットに含まれるボールは3種類。それぞれの異なる特徴や活用方法、健康な手を作るための簡単ガイドはこちらから。
また、以下の動画ではナボソの開発者であるDr.エミリーによるハンドアクティベーションキットの詳しい説明とともに、実際にボールを使ったエクササイズを一緒に実践することができます。
まとめ
身体図式(ボディスキーマ)は、日々の生活や運動の質を左右する重要な要素です。適切な触覚刺激やエクササイズを取り入れることで、身体の感覚を研ぎ澄まし、よりスムーズな動作を実現できます。ハンドアクティベーションキットを活用しながら、触覚の適応力を高めるトレーニングを日常に取り入れてみましょう。
(参照)